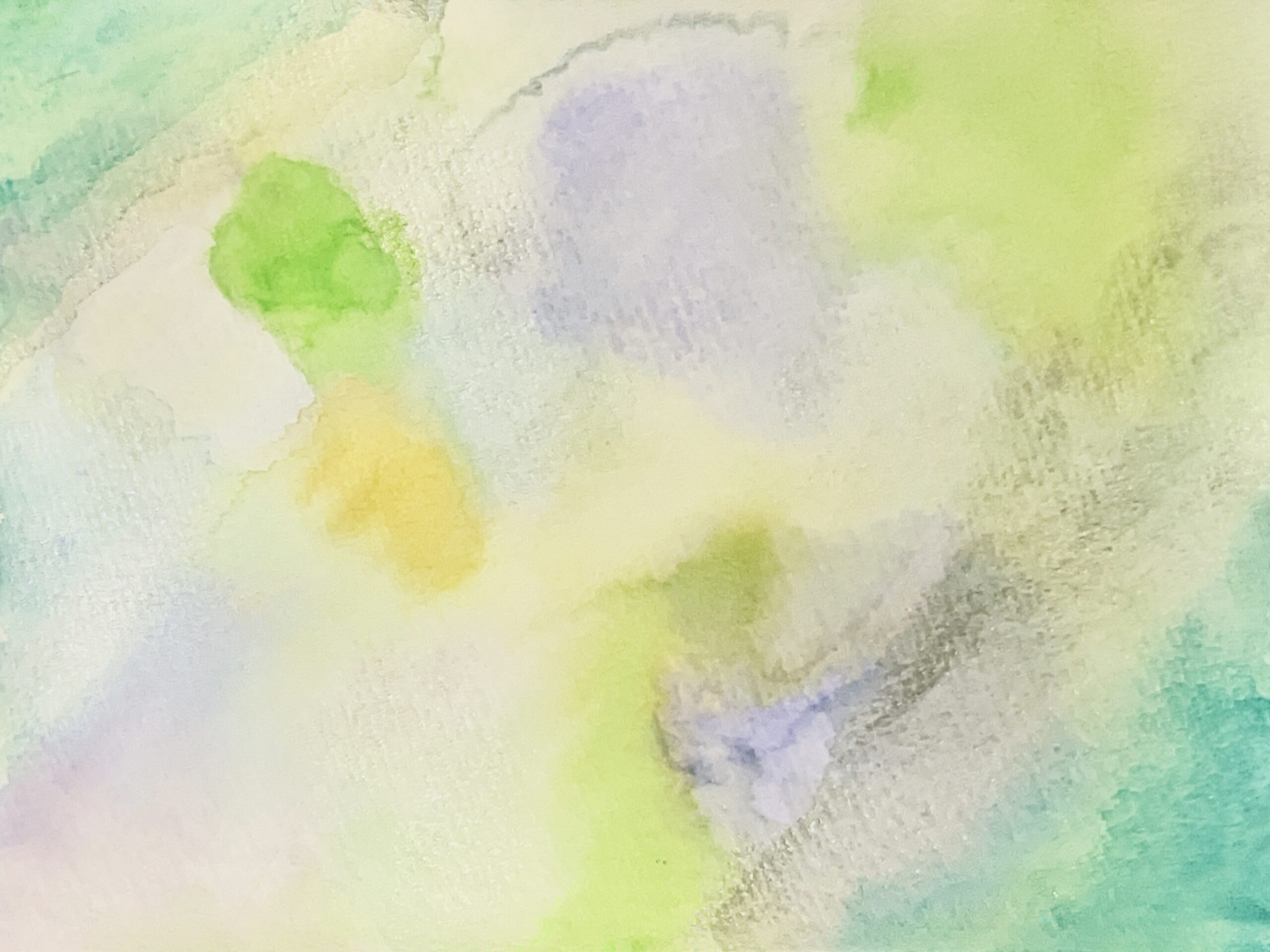自分自身を甘やかさずに振り返れる人に見てもらいたい。
適応障害を患い、有資格者のカウンセラーさんに見ていただきたいと思って臨床心理士の先生の元を尋ねた。
数度目の精神疾患だが、自分の思考回路や人間関係の形成癖が私の心を病ませているという確信があった。
だから、薬を飲んで一時的に回復してもまた心が病むと思い、絶対に薬を飲まずに治すと決めた。
でも、どこがトリガーポイントなのかわからなかったから、それを診てもらいたかった。
こんなことを書いたら自惚れていると思われることを分かった上であえて書くが、
私は自分の見抜く力にそこそこ自信があった。
前の職場でも、先輩や上司から妨害を受けるくらいには評価されていたと思うし、クライアントさんからもありがたい言葉をいただけていた。それは、私が自分自身の嫌なところまで目を逸らさず見つめることができるからだと思っている。
自己評価は、上振れても下振れても、見抜く力を鈍らせる。
自分を解像度高く観る力が、他者を見抜く力の根源だと確信している。
ただ、私は自分を疑う力が強すぎるから、それがたまに迷いを生むデメリットもある。
当時は周りからの批判や強い風当たりを受け、自分を疑う力が強くなり過ぎていたため、冷静な判断ができなくなっていた。(過去を振り返ると、その時に私は精神疾患にかかる)
だから専門家の力を借りたかった。
今までいたスクールのカウンセラーの多くは、今考えても実力のある人ばかりだったが、
その人自身の人生の課題に触れると、途端に弱くなってしまうと感じていた。
目の前のクライアントが自分の課題に触れさせる存在だった場合、無意識に問題から目を逸らしたくなるものだ。
その時に、自分の課題と他者の課題を混同させ、カウンセリングの質が低下する。
この時に重要なのは、どれだけ知識があるか?ではなく
どれだけ早く自分の課題だと気がつき、カウンセリングの質を維持するかだ。
それは心理学の専門家じゃないから仕方がないことだと思った。
だから私は、自分の課題とクライアントの課題を切り分けた上で私の悩みのアプローチ法を一緒に考えてくれる方に出会いたかった。
臨床心理士さんのカウンセリングの違和感
臨床心理士さんの実際のカウンセリングが始まった。
私にとっていちばん有り難かったのは、自分と母の関係が共依存関係にあると教えてもらえたことだった。
それを教えてもらってから母との関係を見た時に、どこがもつれているのかとてもわかりやすくなった。
ただ、今思い返せば結構早い段階で違和感は出ていた。
カウンセリングでは、ほとんど私が母との関係について考察したことを発表する場のようになっていて、
カウンセラーさんはほとんど話さなかった。
SNSで私の考察を読んでいてくれた人はきっと、カウンセリング内容を書いていたと思ったと思うけれど、実はあれはほとんど私が自分で内観した考察結果を書いていただけだった。
私は心理学の専門家ではないけれど、自分が人の悩みを聞く仕事に携わった経験から学んだことがたくさんある。
悩みがいっぱいで頭の中の整理が追いついていない状態の人がカウンセリングに来ると、その時間はほとんどが自分の気持ちを吐き出す場になる。自分の気持ちを吐き出すカウンセリングは、「話を聞いてほしい」気持ちが強い段階の人にはとても大切な時間だ。
でも私が求めていたことは違った。
黙って話を聞いてもらって「わかってもらえている」という承認欲求を満たしてもらうことはもうほとんど必要としていなかった。
むしろ私は要点をかいつまんで話して、残りの時間を目一杯、実際的な解決方法を導き出す話し合いとして使いたかった。
だから毎回、話したい内容を事前に書いて要点だけを伝えて
後の時間を話し合いに使えるように自分なりに準備していっていたのだけれど、
先生の意見は違うようだった。
- 私が事前にまとめてくること
- 簡潔に話を終えること
- 自分の仮説や分析結果を話すこと
それが要らないと言われることが増えた。
はじめは、「今の私にはそれが必要だと判断されたのだろう」と思い先生の仰る通りにしていたのだけれど、
だんだんと違和感のある発言が増えた。
そして、回を重ねるごとに私の人格否定をするような発言が増えた。
未熟さと向き合っても解決しない
これは私が人の相談を受ける現場にいたからわかるのだけれど、
まだ”問い”が立っていない人の悩みは、ほとんどの原因が「見たくない自分」にある。
そういう場合は、遅かれ早かれ
「見たくなかった自分」を直視するまで、どんどん現実が悪化し問題や悩みが増える。
はじめは「私にもまだ自覚していなかったところがあったんだな」と思い内省していたけれど
どんどんと違和感が大きくなった。
自分と向き合わせるために敢えて突きつけているとしたらかなり乱暴なやり方だし、何よりも、
問題の原因が私の未熟さへの無自覚だったのなら指摘されて受け止めれば問題が解決するはず。
「私が自分の未熟さをまだしっかり自覚していないからいけないのかもしれない」と、
まだ見たくない自分はいないか点検を重ねるうちに
その思考が逆に私の自分を疑う癖を助長させ、どんどん自分を追い詰めることになった。
カウンセリングに通うほどに適応障害の症状が悪化する私を見て、
家族と、心理学の大学に通い直している前職の先輩が心配をし始めた。
自分の課題と他人の課題を切り分けるポイントとは
自分の課題を直視せずに誰かのせいにして終わらせると、どこかで必ず似たような出来事が起こる。
だから今回も「カウンセラーさんのせい」にして話を終わらせたくない。
ただ、カウンセリングを重ねるたびに、物静かな先生の感情の起伏を感じるようになった。
それを見て「もしかして先生も私に何かを投影しているのかもしれない(=先生の課題でもあるのかもしれない)」と思い始めた。
自分の課題か相手の課題かを見分けるのは簡単で
「感情が揺れるているかどうか」だ。
自分の課題でなければ落ち着いていられるはずなのに、先生は感情が揺れている。
先生は、回数を重ねるごとに私への当たりがきつくなり、
自分の課題とクライアントの課題を混同させていた前の職場のカウンセラーさんたちと同じ様子が散見されるようになった。
「これは先生が私に課題を投影している」というのがだんだんと確信に変わってきたため
残念だったけれど、辞めることにした。
もちろんこれは私の仮説でしかないので、私が先生をそんなふうに見ていることは伝えなかった。
先生には「少し、今までのカウンセリングでおっしゃっていただいた内容を考える時間が欲しいです」と伝えた。
先生は今までで一番怒っていたし、私の人格否定をされていた時にうっすら感じた嘲笑、見下し、子供扱いの空気が最後に顕著に現れたので、
やはりこれは先生の課題だったんだな、と確信した。
この出来事から、私が適応障害になったもう一つの原因(親子関係以外の)は人から投影をされやすい性質にあると明らかになった。